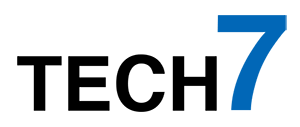「人は自分を正当化するために他を批判するものである。」これは自分の行動や理論に矛盾が生じたときに、他を批判して自分を正当化しようとする行為を指す。
「矛盾が生じたときに」というのがポイントで、この時に行う批判は都合のよい情報を並べ、事実を膨張させたり、無関係の話を持ってくるなど、半ばでっち上げのような状態になることがある。自分がそのような思考に陥っていないかを常に気をつけることは、余計な問題を引き起こさないためには大切なことになるだろう。

先日、スケダチの高広さん(@mediologic)に「認知的不協和」という言葉を教えていただいた。これは正当化しようとする当人の心理状況を説明するものとして当てはまる。Wikipediaによると以下のように説明されている。
認知的不協和は、人が自身の中で矛盾する認知を同時に抱えた状態、またそのときに覚える不快感を表す社会心理学用語。 人はこれを解消するために、自身の態度や行動を変更すると考えられている。有名な例として、イソップ物語のキツネとすっぱい葡萄の逸話が知られる。
わかりやすい例として紹介されているのが、タバコを吸う行為で起こる認知的不協和の例。「タバコを吸うと肺ガンになりやすい」ことを知りながら「タバコを吸う行為」に対して自分自身に矛盾を感じるというものだ。
この不協和から脱するために「禁煙する」という行為を選べば矛盾は解消するが、それが難しいと感じた場合に「喫煙者で長寿の人もいる」「交通事故で死亡する確率の方が高い」という事実を加えることで、矛盾する圧力を弱めようとする。「長寿の人もいる」というのは自分にとって都合の良いデータを引っ張り出しただけだし、「交通事故」に関しては死亡率だけを論点としており本筋ではない。
このような思考でタバコを吸うための論理を展開する形になる。
この説明だけでも、どのようなものであるかが十分伝わると思うが、私がこの考え方に出会った「自分の小さな「箱」から脱出する方法」という本では他人を批判するに至るプロセスについて説明されているので紹介したい。
この本でいうところの「箱」とは、自己正当化イメージをまとった状態と考えて頂ければと思うが、人が箱に入るときには以下のようなプロセスがあると説明している。
- 自分が他の人のためにすべきだと感じたことに背き自分を裏切る
- 自分の感情に背くと、自分の裏切りを正当化する為の視点で他を見るようになる
- 自分を正当化するために、現実を見る目がゆがめられる
- したがって、人は自分の感情に背むいたときに、箱に入る
- やがて箱を持ち歩くようになる
ちょっとわかりにくいので、身近な夫婦のケースで上記のプロセスを紹介しよう。
- 夫が部屋が散らかっているのが気になって、片付けようとしたがやめる。(自分の考えを裏切る)
- 私が片付けないのは仕事が忙しいからだ、自分より時間がある妻はなぜ片付けないのか。(正当化するための視点で他を見る)
- 自分は出来る限りのことをしてるというのにひどい妻だ。そもそも普段から気が利かない、家のことを全然やってくれない(自分の欠点はあげず、相手の欠点だけをあげつらうゆがんだ目、さらに無関係の欠点まで持ち出す)
- 上記の思考で物事を見続ける(箱に入る)
- 「私はよい夫だけど、妻は気が利かない」(箱を持ち歩く、よい夫という根拠もない)
このプロセスでポイントなのは、最初に自分の考えを裏切ることからスタートしていることである。裏切ったことを正当化するために、「なぜそうしないのか」を正当化しようとする。いずれこれを固定化したイメージとして持ち歩いてしまうというものだ。
シンプルな例では、「老人が目の前に立ってるのに席を譲らなかった時」や「エレベーターが閉まる時に人が走っているのが見えたのにそのまま閉めてしまったとき」など、「譲った方がいいなぁ」「開けて待っといたほうがいいなぁ」と思ったことをせず、しなかった理由を考えだすという感じだ。
この箱を持ち歩くというのをもう少し説明すると、例えば「自分は物知りである」という箱に入っていた場合、自分より物知りな人に出会った際に、自分を正当化するために、その人の欠点を探したり、自分が知らない口実を作ったりなど、自己正当化するための理論を展開することになる。
このように、人は無意識の中で自分を正当化するための理論を展開することがあるということを知っておくべきである。これは自分自身を知るうえでも、相手を知るうえでも重要だ。
そして、相手が箱に入っているからといって、自分も箱に入ってしまうと、永遠に分かり合えないことになるので注意が必要だ。
情報に触れる際にも、自分に都合のよいデータばかり見ていないか、自分に都合の悪い情報を批判していないかなど注意する必要があるだろう。
この箱に入らない一番の方法は、最初に自分が「やったほうが良い」と考えたことを裏切らないことだ。
Photo by Phillie Casablanca